「思っていたのと違う…」「周りに馴染めない…」4月に転職したあなたが、5月になって心身の不調を感じているなら、それは「転職5月病」かもしれません。この記事では、転職後の新しい環境で陥りやすい「5月病」の原因、症状、そして今日からできる具体的な対策を分かりやすく解説します。もう一人で悩まず、心と体をケアして、充実した毎日を送るための第一歩を踏み出しましょう。
【無料】面談予約はこちら
転職後の「5月病」とは?

「なんとなく憂鬱…」4月に転職したあなたが、5月になって心身の不調を感じているなら、それは転職後の「5月病」かもしれません。
5月病とは?
一般的に「5月病」とは、新生活がスタートした4月~5月頃に、環境の変化や人間関係のストレスなどによって心身に不調をきたす状態を指します。学生であれば、進学やクラス替え、新入生であれば、学校生活への適応がうまくいかないことなどが原因として挙げられます。大人であれば、新しい職場での人間関係や仕事へのプレッシャー、環境の変化などによって心身のバランスを崩しやすくなります。
なぜ転職後に5月病になるのか?
転職後の5月病は、新しい環境への適応に苦労すること、つまり環境の変化が大きな原因として考えられます。4月に新しい会社に入社し、慣れない仕事や人間関係、新しい環境への期待と不安が入り混じる中で、徐々に心身に疲労が蓄積されていきます。そして、5月に入り、大型連休明けにそれまで抑えていた心身の不調が表面化しやすくなるのです。
転職5月病の症状をチェック
新しい職場での生活が始まり、期待と不安が入り混じる中で、心身に不調を感じ始める人も少なくありません。ここでは、転職5月病の症状をチェックし、自身の状態を客観的に把握するための情報を提供します。当てはまる症状がないか確認してみましょう。
精神的な症状
精神的な症状としては、以下のようなものが挙げられます。
| 精神的な症状 | 詳細 |
|---|---|
| 気分の落ち込み | 以前は楽しめていたことへの興味がなくなり、何をするにも楽しさを感じない。些細なことで落ち込んだり、涙もろくなったりする。 |
| 強い不安感や焦り | 将来への漠然とした不安や、仕事への焦りを感じる。常に何かに追われているような感覚に陥る。 |
| 集中力の低下 | 仕事への集中力が続かず、ミスが増える。物事を考えたり、判断したりすることが難しくなる。 |
| イライラ感の高まり | 些細なことでイライラしたり、怒りやすくなったりする。周囲の人とのコミュニケーションがうまくいかなくなる。 |
| 無気力感 | 何をするにもやる気が起きず、体が重く感じる。何もかもが面倒になり、積極的に行動できなくなる。 |
これらの症状は、精神的なストレスが原因で起こることが多く、放置すると悪化する可能性があります。もし、当てはまる症状が多い場合は、専門家への相談も検討しましょう。
身体的な症状
身体的な症状としては、以下のようなものが挙げられます。
- 不眠や睡眠障害: 寝つきが悪くなったり、夜中に何度も目が覚めたりする。十分に眠っても疲れが取れない。
- 食欲不振や過食: 食欲がなくなり、食事がとれなくなる。または、ストレスから過食に走り、体重が増加する。
- 吐き気や胃痛: 胃の不快感や吐き気を感じる。食欲不振にもつながりやすい。
- 頭痛や肩こり: 頭痛や肩こりが慢性的に続く。体の緊張が原因で起こることが多い。
- 倦怠感: 常に体がだるく、疲れやすい。休息しても回復しない。
これらの身体的な症状は、精神的なストレスだけでなく、生活習慣の乱れも影響している場合があります。規則正しい生活を心がけ、症状が改善しない場合は医療機関を受診しましょう。
転職5月病の原因を徹底分析~よくある4つの原因~

新しい職場での生活が始まり、期待と不安が入り混じる中で、5月病を発症してしまう原因を具体的に見ていきましょう。転職後の5月病は、様々な要因が複雑に絡み合って起こることが多いです。ここでは、主な原因を4つのカテゴリーに分けて解説します。
1.環境の変化への適応
転職後の新しい環境への適応は、5月病の大きな原因の一つです。4月に入社し、新しい仕事内容、人間関係、職場の雰囲気に慣れようと必死に努力する中で、心身に疲労が蓄積されます。新しい環境では、常に気を遣い、緊張感が持続するため、知らず知らずのうちにストレスを抱え込んでしまうものです。また、新しい仕事への慣れや、新しい人間関係の構築には時間がかかります。4月は期待と希望に満ち溢れていても、5月に入り、現実とのギャップを感じることで、精神的な負担が大きくなり、5月病を発症しやすくなります。
具体的には、以下のような状況が考えられます。
- 仕事内容への不慣れ: 新しい仕事に慣れるまでに時間がかかり、ミスをしたり、周囲に迷惑をかけてしまうのではないかという不安を感じる。
- 業務量の増加: 新しい仕事に慣れていないにも関わらず、業務量が増加し、残業が増えるなど、身体的な負担が増加する。
- 通勤時間の変化: 通勤時間が長くなったり、交通機関の遅延などにより、通勤のストレスが増加する。
- 新しい職場環境への違和感: 職場の雰囲気や文化が、自分の価値観や考え方と合わないと感じる。
2.人間関係の悩み
人間関係の悩みも、5月病の大きな原因となります。新しい職場では、上司や同僚とのコミュニケーションが不可欠ですが、良好な関係を築くことは簡単ではありません。特に、以下のような状況は、人間関係のストレスを増大させ、5月病を引き起こしやすくなります。
- コミュニケーション不足: 周囲とのコミュニケーションがうまくいかず、孤立感を感じる。相談相手がいない、相談しにくい環境である。
- 人間関係の摩擦: 上司や同僚との意見の対立、価値観の違いなどにより、人間関係の摩擦が生じる。陰口や仲間はずれなど、精神的な苦痛を感じる。
- ハラスメント: パワーハラスメント、セクシャルハラスメントなど、ハラスメント行為を受けている。我慢してしまい、誰にも相談できない。
- 派閥争い: 職場で派閥争いがあり、巻き込まれる、またはどちらの派閥にも属せず、肩身の狭い思いをする。
3.仕事内容への不満
仕事内容への不満も、5月病の原因の一つです。転職前に抱いていた仕事のイメージと、実際の仕事内容との間にギャップがある場合、不満を感じやすくなります。また、以下のような状況も、仕事へのモチベーションを低下させ、5月病を引き起こす可能性があります。
- 仕事内容のミスマッチ: 自分のスキルや経験と、仕事内容が合わない。やりがいを感じられない。
- 労働条件への不満: 給与、勤務時間、休日など、労働条件に不満がある。残業が多い、休日出勤が多いなど。
- キャリアパスへの不安: 将来的に、この会社でキャリアアップできるのか、不安を感じる。自分の成長を実感できない。
- 評価への不満: 自分の仕事ぶりを正当に評価してもらえないと感じる。
4.理想と現実のギャップ
転職前に抱いていた理想と、現実とのギャップも、5月病の大きな原因となります。転職活動中は、良い面ばかりを見てしまいがちですが、実際に働き始めると、様々な問題に直面することがあります。理想と現実のギャップが大きいほど、落胆も大きく、5月病を発症しやすくなります。
具体的には、以下のようなギャップが考えられます。
- 企業のイメージとのギャップ: 企業のウェブサイトや求人情報から受けていた印象と、実際の企業の雰囲気や文化が異なる。
- 仕事内容のイメージとのギャップ: 自分が想像していた仕事内容と、実際の仕事内容が異なる。単調な作業が多い、責任が重すぎるなど。
- 人間関係のイメージとのギャップ: 職場の人間関係が、自分が思っていたよりもギスギスしている。思っていたような協力体制がない。
- 給与や待遇のイメージとのギャップ: 給与や福利厚生など、待遇面で不満がある。残業代が少ない、昇給が見込めないなど。
これらの原因は、単独で作用するだけでなく、複合的に絡み合って、5月病を引き起こすこともあります。自身の状況を客観的に分析し、どの原因が強く影響しているのかを把握することが、5月病を乗り越えるための第一歩となります。【無料】面談予約はこちら
脱出!転職5月病からの抜け出す具体的な方法

4月に転職し、新しい環境に慣れようと頑張っているのに、心身の不調を感じているあなたへ。ここでは、転職5月病から脱出し、再び前向きに仕事に取り組むための具体的な対策を4つのステップでご紹介します。あなたの状況に合わせて、できることから始めていきましょう。
休息とリフレッシュ
まずは、心と体を休ませることが大切です。休日はしっかりと休息を取り、心身の疲労を回復させましょう。質の高い睡眠も重要です。寝る前にリラックスできるような工夫を取り入れましょう。例えば、ぬるめのお風呂に浸かったり、アロマを焚いたり、ストレッチをしたりするのも良いでしょう。また、趣味や好きなことに没頭する時間も作りましょう。映画鑑賞、読書、音楽鑑賞など、自分が楽しめることで気分転換を図りましょう。近所の公園を散歩したり、自然の中で過ごす時間もおすすめです。太陽の光を浴びることで、セロトニンの分泌が促進され、気分が明るくなります。
生活習慣の見直し
規則正しい生活習慣は、心身の健康を保つ上で非常に重要です。まずは、食事の時間を見直しましょう。栄養バランスの取れた食事を規則正しく摂ることで、体の内側から健康をサポートします。朝食を抜くと、集中力の低下やイライラにつながることがあります。必ず食べるようにしましょう。昼食は、短時間で済ませず、ゆっくりと時間をかけて食べるようにしましょう。夜食は控えめにし、寝る2時間前には食事を済ませるようにしましょう。次に、適度な運動を取り入れましょう。軽い運動でも、気分転換になり、ストレスを軽減する効果があります。ウォーキングやジョギング、ヨガなど、無理なく続けられる運動を見つけましょう。週に数回、30分程度の運動を目標にしてみましょう。最後に、十分な睡眠時間を確保しましょう。睡眠不足は、心身の不調を引き起こす原因となります。毎日同じ時間に寝起きし、7~8時間の睡眠時間を確保するようにしましょう。寝る前にカフェインを摂取するのは避け、リラックスできる環境を整えましょう。
専門家への相談
一人で抱え込まず、専門家に相談することも大切です。精神的な不調を感じたら、まずは心療内科や精神科を受診してみましょう。医師は、あなたの症状を詳しく診断し、適切な治療法を提案してくれます。必要に応じて、薬物療法やカウンセリングが行われます。カウンセリングも有効な手段です。臨床心理士やカウンセラーは、あなたの悩みを聞き、心のケアをしてくれます。専門家のアドバイスを受けることで、問題解決の糸口が見つかることもあります。
また、仕事のことにおいてはキャリアのプロであるキャリアコンサルタントに相談するのも良いでしょう。転職後のキャリアに関する悩みや不安を相談することで、今後のキャリアプランを立てるヒントが得られます。信頼できる人に話を聞いてもらうだけでも、心が楽になることがあります。家族や友人、同僚など、誰でも構いませんので、自分の気持ちを話してみましょう。話すことで、自分の気持ちを整理し、客観的に状況を把握することができます。
周囲への相談
周囲への相談も、問題解決の第一歩です。まずは、信頼できる上司や同僚に、今の状況や悩みを打ち明けてみましょう。相談することで、周囲の理解を得て、サポートを受けやすくなります。上司には、仕事への取り組み方や課題を具体的に伝えましょう。同僚には、日頃からコミュニケーションを取り、信頼関係を築いておくことが大切です。会社の相談窓口を利用するのも良いでしょう。専門のカウンセラーが秘密厳守で相談に乗ってくれます。相談窓口をためらっている場合は、人事部に相談してみましょう。状況に応じたサポートや、部署異動、休職などの提案をしてくれます。家族や友人に相談するのも良いでしょう。あなたのことをよく知る人に話を聞いてもらうことで、心が軽くなることもあります。しかし、相談する相手は、あなたの状況を理解し、親身になってくれる人を選びましょう。
これらの対策を実践することで、転職5月病から脱出し、新しい職場での生活をより良くすることができます。焦らず、自分のペースで一つずつ取り組んでいきましょう。もし、状況が改善しない場合は、専門家への相談も検討しましょう。一人で悩まず、周囲のサポートを受けながら、前向きに進んでいきましょう。
5月病に関するよくある質問
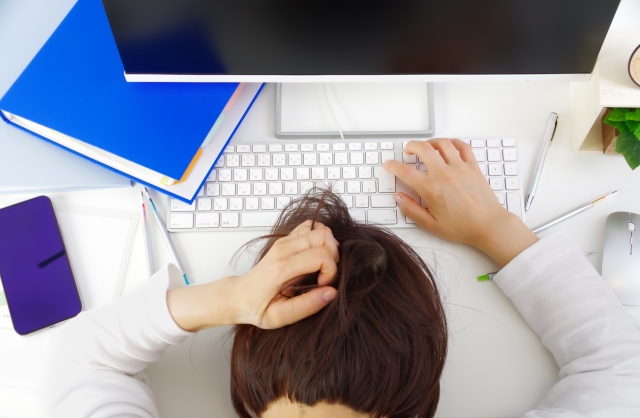
転職後の5月病について、多くの方が抱く疑問とその答えをまとめました。あなたの疑問を解消し、より良い一歩を踏み出すためのヒントにしてください。
Q1:転職してすぐに辞めても良い?
転職してすぐに「思っていたのと違う」と感じ、辞めたいと考えることは珍しくありません。しかし、すぐに辞める前に、以下の点を検討してみましょう。
- 辞める前に確認すること: まずは、なぜ辞めたいのか、その原因を具体的に分析しましょう。仕事内容、人間関係、労働条件など、問題点を明確にすることで、本当に辞めるべきか、改善の余地があるのかを判断できます。上司や同僚に相談したり、キャリアコンサルタントに相談したりするのも良いでしょう。客観的な意見を聞くことで、冷静な判断ができます。
- 早期離職のリスク: 早期離職は、キャリアに影響を与える可能性があります。転職回数が増えると、採用に不利になる場合もあります。しかし、無理をして働き続けることが、心身の健康を損なう可能性もあります。あなたの状況を最優先に考え、慎重に判断しましょう。
- 辞める場合の注意点: 辞める場合は、退職理由を明確にし、円満退職を目指しましょう。転職先が決まっていない場合は、生活費の確保や、次の転職活動の準備も必要です。退職後の手続きについても、事前に調べておきましょう。
Q2:転職5月病はいつまで続く?
転職5月病の期間は、人によって異なります。数週間で症状が改善する人もいれば、数ヶ月間続く人もいます。しかし、適切な対策を講じることで、症状を改善し、早期の回復を目指すことができます。
- 回復までの期間: 5月病の期間は、原因や症状の程度、個人の性格や環境などによって異なります。焦らず、自分のペースで回復を目指しましょう。専門家のアドバイスを受けながら、適切な対策を続けることが大切です。
- 症状が長引く場合: 症状が長引く場合は、専門家への相談を検討しましょう。心療内科や精神科を受診したり、カウンセリングを受けたりすることで、症状の原因を特定し、適切な治療を受けることができます。また、キャリアコンサルタントに相談し、キャリアプランを見直すことも有効です。
- 再発の可能性: 一度回復しても、環境の変化やストレスなどによって、再発する可能性があります。再発を防ぐためには、日頃から心身の健康に気を配り、ストレスを溜めないように工夫することが大切です。自分のストレスの原因を把握し、それに対する適切な対処法を身につけましょう。
Q3:転職5月病で会社を休むことは可能?
転職5月病の症状が辛く、仕事に行けないと感じる場合は、会社を休むことも可能です。しかし、休む前に、以下の点を考慮しましょう。
- 休むことのメリットとデメリット: 休むことで、心身を休ませ、症状の悪化を防ぐことができます。しかし、休むことで、仕事への遅れや、周囲への負担が増える可能性があります。休む前に、上司や同僚に相談し、理解を得ることが大切です。
- 休むための手続き: 会社を休む場合は、事前に上司に連絡し、休暇の手続きを行いましょう。診断書が必要な場合もありますので、事前に確認しておきましょう。休んでいる間も、会社との連絡を密にし、復帰に向けて準備を進めましょう。
- 休んだ後の対応: 会社を休んだ後は、無理をせず、自分のペースで仕事に復帰しましょう。復帰後も、体調に異変を感じたら、無理せず休むようにしましょう。周囲の理解を得ながら、徐々に仕事に慣れていくことが大切です。
これらの質問と回答を通して、転職5月病に関する疑問を解消し、あなたの状況に合った対策を見つけることができるでしょう。一人で悩まず、周囲のサポートを受けながら、前向きに進んでいきましょう。【無料】面談予約はこちら
一歩を踏み出して今のモヤモヤを克服しよう!

4月に転職し、新しい環境でスタートしたものの、5月に入り心身の不調を感じ始めたあなたへ。この記事では、転職5月病の原因、症状、そして今日からできる具体的な対策を解説してきました。
転職後の環境変化や人間関係の悩み、仕事内容への不満など、様々な要因が絡み合い、5月病を引き起こします。しかし、適切な対策を講じることで、必ず乗り越えることができます。心と体を休ませ、規則正しい生活習慣を心がけること。そして、専門家への相談や周囲への協力を得ることで、前向きな一歩を踏み出すことができます。
この記事が、あなたの転職5月病克服の助けとなり、充実した毎日を送るための一助となれば幸いです。一人で悩まず、積極的に行動を起こし、新しいキャリアを切り開いていきましょう。
弊社は、20~30代の女性に特化した転職エージェントとして、女性特有のお悩みを十分理解したうえで細やかなご提案を強みとしています。転職やキャリアなどにお悩みがありましたら、一人で悩まず、まずは私たちにご相談ください。あなたのキャリアを一緒に考え、新たな一歩をサポートします。









コメント