「女性の社会進出」「女性が輝く社会」という言葉を聞くようになってからしばらく時がたちました。安倍内閣の最重要施策として“女性活躍推進法”が成立し、女性が活躍するための政策や指針が多数策定されてきたなか、企業もこの政策をもとに積極的に女性を採用し労働環境整備に取り組み、実際に活躍の場を広げた女性も増えています。
女性を採用することは企業にとってもプラスになることが多いのですが、実際には「女性をなかなか採用できない」「むずかしい」と感じている担当者も多いようです。現時点ではすべての女性が活躍できる環境になったとはいえませんが、女性を採用するメリットや女性採用を実現するために企業が取り組むべきことを考え、このような社会的状況下でも負けない人材育成、企業価値向上を目指しましょう。
女性を採用するメリット

まずは、企業が女性を採用するメリットを考えてみましょう。女性を採用することが企業にとってどのようなメリットをもたらすのか、たくさんのデータにも表れているようです。
1.優秀な人材を確保できる
現在、大学に進学する人も多く、将来を見据えて専門知識を身に付ける人が増えました。高学歴であることが優秀なビジネスマンの定義ではありませんが、性別にかかわらず優秀な人材を確保できるのは企業にとって大きなメリットといえます。
2.生産性が向上する
公益財団法人日本生産性本部の調査によれば、「女性の活躍によって生産性が向上する」というデータもあります。約20%が「業績向上の要因の一つになっている」、約30%が「業績向上へのつながりはみられないが、組織が活性化するなど変化がある」と答えており、約50%の企業で「女性の活躍による変化がみられる」と回答しています。(参照:公益財団法人日本生産性本部「第8回「コア人材としての女性社員育成に関する調査」 結果概要」)
3.多様性が生まれる
たとえば、男性の多い職場では、女性を採用することで女性目線の意見を取り入れることができ、新たな文化や価値観が生まれることもあるかもしれません。さまざまな人の意見を取り入れることで、多様性のある企業へと成長する可能性も高まります。
4.企業認知度が向上する
また、実際に女性が働いていることで厚生労働省など公的機関からも「女性活躍を推進している会社」として認めてもらえるかもしれません。公的機関からの認定は、就活生や転職者からも「信頼性の高い企業」だとよい印象を持ってもらえます。
5.企業価値を向上できる
優秀な人材を確保でき多様性が生まれ、企業としての認知度も向上し、周囲に認められるようになると、おのずと企業価値も向上していくでしょう。短期的な利益ではなく、企業としての社会的価値を生みだし、企業全体の成長に大きく関与するはずです。
日本の女性の社会進出の現状

日本の女性の社会進出は、近年進展を見せていますが、依然として課題も多く存在します。ここでは、厚生労働省や内閣府などの公式データを参照し、具体的な数値を提示しながら現状と課題を分析していきましょう。
1. 就業率
女性の就業率は上昇傾向ですが、男性との差は依然として大きいといえます。また、下記では結婚・出産・育児などをきっかけに、多くの女性が職場を離れるか、働き方を制限せざるを得ない状況にあることを示しています。
-
2022年の女性の就業率は69.6%、男性の就業率は78.5% (厚生労働省「労働力調査」)
-
女性の就業率は1990年の51.9%から上昇傾向だが、男性との差は依然として10%弱ある
-
25~34歳の女性の就業率は80%を超えていますが、35~44歳で大きく低下、その後も緩やかに低下 (厚生労働省「労働力調査」)
2. 管理職比率
女性の管理職比率は低く、管理職に就いたとしても長く続けることが難しいのが状況です。
-
2022年の女性の管理職比率は15.2% (内閣府「男女共同参画白書」)
-
OECD諸国平均の27.4%を大きく下回り、先進国の中では低い水準 (OECD「Gender Data Portal」)
-
45~54歳の女性の管理職比率が最も高く、その後は低下 (内閣府「男女共同参画白書」)
3. 非正規雇用比率
女性の非正規雇用比率は高く、一度正規雇用でなくなると再度正規雇用に戻ることが難しい状況です。また、キャリアアップの機会も少ない傾向にあります。
-
2022年の女性の非正規雇用比率は38.7% (厚生労働省「労働力調査」)
-
男性の15.5%と比べて、約2倍以上の数値
4. 賃金格差
男女間の賃金格差は依然として存在します。先述した、雇用形態の違いやキャリアアップの機会の少なさなども影響しています。
-
2022年の女性の賃金は、男性の賃金の約73% (厚生労働省「賃金構造基本統計調査」)
5. 育児休業取得率
男性の育児休業取得率は低く、制度としてもうまく活用されていない現状があります。これは、男性の育児休業取得に対する社会的な意識や制度的な課題などが要因と考えられています。
-
2022年の女性の育児休業取得率は82.5% (厚生労働省「育児休業取得状況」)
-
一方、男性の育児休業取得率は14.2%にとどまる
日本の女性の社会進出には課題が多い
日本の女性の社会進出は、依然として課題が多く、男性との間に大きな格差が存在することがデータからも明らかです。女性の就業率は上昇傾向にある一方で、管理職比率や賃金は男性に比べて低く、非正規雇用比率は高い状況です。また、男性の育児休業取得率も低い水準にとどまっています。これらの課題を解決するためには、企業や社会全体の意識改革と制度的な整備が不可欠です。
【国際比較】日本の女性と海外の女性の社会進出の違い

日本の女性の社会進出は、国内データだけでなく国際的なデータと比較することでより客観的な評価ができます。ここでは、OECD諸国を例に、日本の状況を国際的に比較し現状と課題を分析します。
1. 就業率
-
2022年の日本の女性の就業率は69.6%
-
OECD諸国平均の68.3%をわずかに上回っている (OECD「Gender Data Portal」)
-
しかし、日本の女性の就業率は35~44歳で大きく低下する傾向
-
OECD諸国平均と比べて、この年齢層での就業率が低い
2. 管理職比率
-
2022年の日本の女性の管理職比率は15.2%
-
OECD諸国平均の27.4%を大きく下回る (OECD「Gender Data Portal」)
3. 非正規雇用比率
国際的にも、日本の女性が非正規雇用で働く割合が高いこと、そして非正規雇用から正規雇用への転換が難しい状況
-
2022年の日本の女性の非正規雇用比率は38.7%
-
OECD諸国平均の25.2%を大きく上回る (OECD「Gender Data Portal」)
4. 賃金格差
日本の男女間の賃金格差は、OECD諸国平均と比較しても依然として大きいことが分かります。
-
2022年の日本の女性の賃金は、男性の賃金の約73% (厚生労働省「賃金構造基本統計調査」)
-
OECD諸国平均の男女間の賃金格差は、男性の賃金の約82% (OECD「Gender Data Portal」)
5. 育児休業取得率
女性の育児休業取得率は上昇し、国際的に比較してもほぼ藤堂です。一方で、日本の男性が育児休業を取得しにくい社会的な状況であることが下記のデータから見て取れます。
-
2022年の日本の女性の育児休業取得率は82.5%
-
OECD諸国平均の81.5%とほぼ同等 (OECD「Gender Data Portal」)
-
一方、日本の男性の育児休業取得率は14.2%
-
OECD諸国平均の72.7%を大きく下回る (OECD「Gender Data Portal」)
国際的にみても課題が山積み
日本の女性の社会進出は国際的なデータと比較しても依然として課題が多く、特に管理職比率、非正規雇用比率、男性の育児休業取得率はOECD諸国平均を大きく下回っています。これらの課題を解決するためには、企業や社会全体の意識改革と制度的な整備が不可欠です。
女性活躍を進めるために企業がやるべきこと
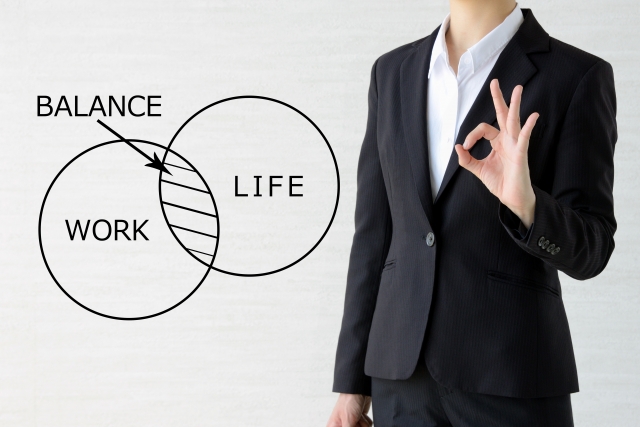
女性の社会進出を促進し、真の意味で多様な人材が活躍できる組織を実現するためには、企業は単なる制度の導入だけでなく、意識改革と具体的な行動を伴う取り組みが必要です。以下に、企業が取り組むべき具体的なポイントをまとめます。
1. 柔軟な働き方と制度の導入
まずは、女性を含め、社員がライフイベントに対応するワークスタイルを整備することが求められます。
|
施策 |
内容 |
|---|---|
|
時間や場所にとらわれない働き方 |
テレワーク、フレックスタイム制、リモートワークなどを導入し、従業員が自分のライフスタイルに合わせて柔軟に働ける環境を提供します。 |
|
育児・介護休暇制度 |
取得期間の延長、給与保障の向上、取得しやすい制度設計などを検討し、従業員が安心して休暇を取得できる環境を作ります。 |
|
休暇取得後の職場復帰支援 |
職場復帰後の業務サポート、スキルアップのための研修プログラムなどを提供し、安心して仕事に復帰できる体制を整えます。 |
|
育児・介護と仕事の両立支援 |
育児休暇中のサポート体制、託児所や保育所の利用支援、育児に関する情報提供などを提供し、仕事と育児を両立しやすい環境を作ります。 |
2. 職場環境の改善
また、性別による差別意識や偏見・思い込みなどのジェンダーバイアスを解消し、誰もが働きやすい環境を整備することも大切です。
|
施策 |
内容 |
|---|---|
|
女性リーダー育成プログラムの導入 |
女性社員のリーダーシップ育成を支援するプログラムを導入し、女性が管理職に就きやすい環境を作ります。 |
|
意識改革のための研修プログラムの導入 |
無意識のジェンダーバイアスや、多様性に関する理解を深めるための研修プログラムを導入し、従業員の意識改革を促進します。 |
|
女性が活躍しやすい職場環境づくり |
女性の意見が尊重され、発言しやすい雰囲気づくり、女性社員向けのメンター制度などを導入します。 |
|
ダイバーシティ&インクルージョン(D&I)推進 |
多様性を受け入れ、包容性のある組織文化を構築し、誰もが自分らしく活躍できる環境を目指します。 |
3. 能力開発とキャリアアップ支援
また、女性の潜在能力を引き出し、成長を支援するための支援制度を整備することも必要です。
|
施策 |
内容 |
|---|---|
|
キャリアパス設計 |
女性社員のキャリアプランを支援し、将来の目標達成をサポートするプログラムを導入します。 |
|
リーダーシップ育成 |
リーダーシップ育成プログラムへの積極的な参加促進、女性社員がリーダーシップを発揮できる機会を積極的に提供し、キャリアアップを支援します。 |
|
スキルアップ研修 |
女性社員が専門性を高め、キャリアアップできるための研修プログラムを充実させます。 |
|
意見・要望の反映 |
女性社員の声を積極的に聞き取り、職場環境改善や事業戦略に反映させます。 |
4. 公平な評価制度の導入
そして、能力と貢献度に基づいた評価体制を構築することも大切なことです。公平な評価制度は、社員のモチベーションや成果に直結します。
|
項目 |
内容 |
|---|---|
|
評価制度 |
客観的な評価基準に基づいた評価制度の導入(性別、年齢、ライフスタイルに関係なく能力と貢献度に基づく) |
|
昇進・昇格 |
昇進・昇格基準の明確化と透明化、女性社員への公平な機会提供 |
|
賃金 |
能力や貢献度に基づいた賃金体系の導入による男女間の賃金格差解消 |
5. 社外との連携
また、女性活躍推進に関する情報収集とネットワークを構築することも欠かせません。社会全体で、女性のキャリア支援をすることが大切です。決して昇進やキャリアアップだけではなく、女性も自らが望むキャリアを実現しようとすることができる、その意識を社会全体で持つことの重要性を示しています。
|
取り組み内容 |
詳細 |
|---|---|
|
外部機関との連携 |
女性活躍推進に関する外部機関や団体と連携し、最新の情報を収集し、自社における取り組みを強化します。 |
|
セミナー・イベントへの参加 |
社内研修だけでなく、外部セミナーやイベントに参加することで、最新の動向を把握し、新たな知見を習得します。 |
|
外部ネットワーク構築支援 |
女性社員が外部ネットワークを構築できる機会を提供し、活躍の場を広げます。 |
企業が女性の社会進出を促進し、多様な人材が活躍できる組織を実現するためには、上記のような具体的な取り組みを継続的に行うことが重要です。単なる制度の導入だけでなく、意識改革と行動を伴う取り組みが必要がです。
キャリアを活かせる環境づくりを!

女性が仕事と家庭をバランスよく両立できるかは、周囲の理解や支援によってかわります。優秀な女性を採用し、育成してきた企業としても、優れた人材を逃すのはもったいないことです。企業は、研修や資格取得の支援をはじめ、女性がキャリアや経験を活かせる環境づくりを目指しましょう。
採用課題の解決はクラスへご相談ください
「自社で活躍できる女性を積極的に採用したい」「女性を採用するうえでの課題を解決する方法がよくわからない」など、お悩みがありましたら、株式会社クラスへご相談ください。弊社は、関西で唯一、女性に特化した人材紹介サービスをおこなっております。とくに、20~30代の優秀な若手世代のご提案には自信があり、創業以来多くの企業様の採用課題を解決してきた実績がございます。人材採用によって、貴社の課題を解決していけるよう尽力させていただきます。女性の採用を積極的にお考えの企業様は、ぜひクラスへご相談ください。









コメント